【注意喚起】MACRO MARKETSは危険?出金拒否・安全性・評判・スプレッドを徹底検証
今回検証するのは、近年アジア圏を中心に利用者が急増しているとされるMACRO MARKETS(マクロ・マーケッツ)です。
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:「デリバティブって何?」「なんだか難しそう…」そんな不安を抱えていませんか?この記事では、投資初心者の方向けにデリバティブの仕組みとリスクをわかりやすく解説。先物、オプション、CFDといった主要な取引の種類から、レバレッジの仕組み、よくある疑問まで網羅。デリバティブに対する漠然とした不安を解消し、賢く投資を始めるための第一歩を踏み出しましょう。
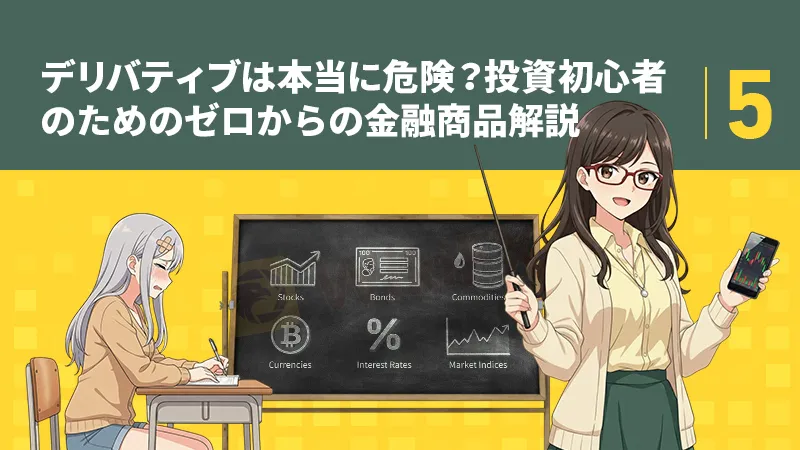
投資の世界に足を踏み入れると、「株式」「債券」「投資信託」など、様々な専門用語に出会いますよね。
そして、その中でもひときわ耳慣れない、ちょっと怖い響きの言葉が「デリバティブ」です。
「デリバティブ?なんだか難しそう…」「プロの人が使うんでしょ?」「リスクが大きそうだし、自分には関係ないかな…」
そう思われるかもしれません。しかし、デリバティブは実は私たちの身近な考え方と深くつながっています。
たとえば、スーパーで「今予約すれば、夏に採れたてのももを特別価格で買えます」というサービス。これは、将来の商品価格を今のうちに決めておくという点で、デリバティブの基本的な考え方と同じです。
この記事では、そんなデリバティブの仕組みとリスクを、投資初心者の皆さんにも分かりやすく、そして誠実にお伝えします。この記事を読み終える頃には、デリバティブに対する漠然とした不安が和らぎ、金融市場がより身近に感じられるはずでしょう。
まず、デリバティブという言葉を分解してみましょう。
・Derive(デライブ):英語で「〜から派生する」という意味です。
・Derivative(デリバティブ):つまり、「派生するもの」という意味になります。
何から派生するのかというと、それは「原資産(Underlying Asset)」と呼ばれる、もとになる金融商品です。原資産には、株式、債券、為替、商品(コモディティ)などがあります。
デリバティブは、これらの原資産の価格が変動することで、その価値が決まります。例えるなら、主役である原資産の「影」のような存在です。影の長さや形が主役の動きによって変わるように、デリバティブの価値も原資産の価格に連動して動きます。
デリバティブ取引には、主に3つの目的があります。
・ヘッジ(リスク回避)
これがデリバティブの本来の目的です。将来の価格変動リスクを避けるために使われます。
例: 農家が将来の価格下落を懸念し、今のうちに固定価格で野菜を売る契約を結ぶ。
・投機(利益追求)
将来の価格を予測し、その価格変動を利用して利益を得ることを目的とします。個人投資家の多くは、この目的で取引を行います。
・アービトラージ(裁定取引)
異なる市場間で生じるわずかな価格差を利用して、リスクを抑えながら利益を得る取引です。
「デリバティブなんて、自分には無縁だ」
そう思われるかもしれませんが、実はその考え方は私たちの身の回りにたくさん隠されています。
例えば、皆さんが大好きなアーティストのコンサートチケットを想像してみてください。半年後に開催されるコンサートのチケットを、先行予約で今のうちに手に入れました。この時、あなたは将来の「コンサートを鑑賞する」という権利を、今のうちに確保したことになります。
この権利には価値があります。もしそのアーティストがテレビで大ブレイクし、チケットが瞬く間に完売した場合、先行予約の権利は非常に価値のあるものになりますよね。逆に、もしアーティストが活動休止を発表したら、チケットの価値は下がってしまうかもしれません。
これは、将来の価値を今のうちに確定させる、というデリバティブの基本的な考え方と全く同じなんです。
デリバティブには様々な種類がありますが、ここでは初心者の方がまず知っておくべき代表的なものを4つご紹介します。
先物取引は、将来の特定の日に、特定の価格で、特定の資産を売買することを約束する取引です。
想像してみてください。あなたは農家で、半年後に収穫する米を売ろうと考えています。半年後の米の価格がどうなっているか分からず不安です。そこで、半年後に100kgの米を100,000円で売るという契約を、買い手と今のうちに交わしておきます。これが先物取引です。
売り手(農家):価格の下落リスクをヘッジできる。
買い手(お米屋さん):価格の上昇リスクをヘッジできる。
このように、先物取引は本来、価格変動リスクを避けるための「ヘッジ」目的で使われていました。しかし、将来の価格変動を予測して利益を得る「投機」目的で使われることが多く、価格が予想通りに動けば大きな利益を得られますが、予想に反すれば大きな損失につながります。
オプション取引は、将来の特定の日に、特定の価格で、特定の資産を売買する「権利」を売買する取引です。
先物取引との最大の違いは「義務」か「権利」かという点です。先物取引は契約した時点で売買の「義務」が生じますが、オプション取引では「権利」を得るだけで、その権利を行使するかどうかは自由です。
オプションには、大きく分けて2つの種類があります。
コール・オプション(買う権利):将来、特定の資産を特定の価格で「買う」権利
プット・オプション(売る権利):将来、特定の資産を特定の価格で「売る」権利
この「権利」を手に入れるために支払う費用を「プレミアム」と呼びます。例えば、あなたはトヨタの株を将来1株3,000円で買う権利を、100円のプレミアムを払って手に入れました。もし将来トヨタの株価が4,000円に上がれば、あなたは3,000円で株を買う権利を行使し、すぐに4,000円で売ることで利益を得られます。しかし、株価が2,000円に下がった場合、あなたは権利を行使せず、プレミアムの100円を失うだけで済みます。
オプション取引は、損失をプレミアムの金額に限定できる一方で、大きな利益を狙える可能性があります。しかし、その仕組みは複雑で、取引戦略も多岐にわたるため、初心者には少しハードルが高いかもしれません。
スワップ取引は、将来の一定期間にわたって、キャッシュフロー(お金の流れ)を交換する取引です。
これは企業や金融機関が主に利用する取引で、例えば「変動金利」と「固定金利」を交換する金利スワップが有名です。ある企業が変動金利で借入をしていて、将来の金利上昇リスクを懸念しているとします。そこで、別の企業とスワップ契約を結び、変動金利の支払い義務と固定金利の支払い義務を交換します。
スワップ取引は、将来の不確実性を軽減するために使われることが多く、個人投資家が直接取引することはあまりありません。
CFD(Contract for Difference)とは、「差金決済取引」のことです。これは、実際に原資産を保有することなく、買い付け時と売却時の価格差のみを現金で決済する取引です。
例えば、日経平均株価のCFDを取引する場合、実際に日経平均株価を構成する企業群の株式を保有するわけではありません。日経平均株価が上がると予想して買い、実際に上がればその差額分が利益となり、下がれば差額分が損失となります。
CFDは、株価指数、商品、個別株、為替など、幅広い原資産を対象に取引できます。また、レバレッジを効かせることができ、売りから入る(空売り)ことも簡単にできるため、短期的な価格変動を狙った投機的な取引によく利用されます。
デリバティブを語る上で、絶対に避けては通れないのが「レバレッジ」です。
レバレッジとは、「てこの原理」を意味します。つまり、少ない資金(証拠金)で、その何倍もの金額の取引ができる仕組みのことです。
例えば、レバレッジが10倍の取引で10万円を投資した場合、あなたは100万円分の取引を行うことができます。
・もし予想通りに1%価格が上昇すれば、100万円の1%にあたる1万円の利益が得られます。投資額10万円に対して10%のリターンです。
・しかし、もし予想に反して1%価格が下落すれば、100万円の1%にあたる1万円の損失となります。投資額10万円に対して10%の損失です。
このように、レバレッジは大きなリターンを狙える一方で、損失も一気に拡大するリスクをはらんでいます。場合によっては、預けた資金以上の損失が発生し、追加で資金を支払う義務(追証)が生じることもあります。
「レバレッジは両刃の剣」。このことを常に心に留めておかなければなりません。
「デリバティブは危険だ」とよく言われますが、それはデリバティブ自体が危険なのではなく、「その仕組みを十分に理解せず、安易にレバレッジをかけて取引すること」が危険なのです。
デリバティブ取引そのものが詐欺というわけではありません。
詐欺の多くは、デリバティブ取引を装った悪質な業者やプラットフォームが原因です。
世界的に信頼されている金融当局のライセンスを持たないブローカーや、実態が不透明な業者も残念ながら存在します。以下を参考に、ご自身の目で信頼できる取引先を見極めることが非常に重要です。
日本の金融庁はもちろん、米国のCFTC、英国のFCAなど、厳格な規制当局のライセンスを保有しているかを確認しましょう。
会社の住所、連絡先、代表者の情報などが明確に公開されているか。
手数料やスプレッドなど、隠れたコストがないか事前に確認しましょう。
万が一のトラブルに備え、日本語でのサポート窓口や担当者がいるかどうかも大切なポイントです。
また、実際に取引を始める前に、デモトレードで使い勝手を試すことを強くお勧めします。ご自身が直感的に使いやすいと感じるプラットフォームを選ぶことが、取引を継続する上で非常に重要です。

間違った業者選びは、資産を失うリスクすらあります。WikiFXでは、各業者のライセンス情報、規制状況、利用者の口コミ評価まで幅広く網羅し、信頼性の高いFX業者を見極めるための情報を徹底的に比較・検証しています。
デリバティブ取引には、その性質上、いくつかの重要なリスクが存在します。
リスク1:高い価格変動リスク
デリバティブは、元となる資産の価格変動に連動して大きく価格が動きます。特に、レバレッジ(少ない資金で大きな取引ができる仕組み)をかけると、予想と反対の方向に価格が動いた場合、元本を大きく上回る損失を被る可能性があります。デリバティブが「投機的な商品」と言われるのは、この高いリスクが理由です。
リスク2:仕組みの複雑さ
デリバティブの種類は多岐にわたり、中には複雑な設計がされた商品も存在します。仕組みを完全に理解しないまま取引を始めると、想定外の事態に直面し、大きな損失につながることがあります。特に、店頭デリバティブ(OTC)は、取引相手が契約を履行しない「カウンターパーティリスク」も存在するため、注意が必要です。
デリバティブ市場は、個人投資家だけでなく、様々なプロフェッショナルな参加者によって成り立っています。
・機関投資家(年金基金、ヘッジファンドなど)
主に保有資産の価格変動リスクを避ける「ヘッジ」目的でデリバティブを利用します。
・投機家(トレーディング会社、個人投資家など)
将来の価格を予測し、利益を上げる「投機」を目的としています。個人投資家の多くは、この投機家にあたります。
・アービトラージ(裁定取引)を行う専門家
異なる市場間で生じるわずかな価格差を利用して、リスクを抑えながら利益を追求します。
デリバティブは、これらの様々な目的を持つ参加者によって取引されることで、市場の流動性を生み出しています。
デリバティブは、うまく使えば投資の世界を広げる素晴らしいツールです。しかし、その力を過信せず、常に謙虚な姿勢で学ぶことが大切です。
包丁も、使い方を知らなければ怪我をします。デリバティブもそれと同じです。その危険性を正しく理解し、自己資金を管理し、ルールを守って取引すれば、あなたの投資の選択肢を広げる強力なツールになり得ます。
もしデリバティブに興味を持ったなら、以下のステップを試してみてください。
・デリバティブの種類や仕組みを十分に理解する
・少額の資金で、デモトレードから始める
・自己資金に余裕を持った状態で、レバレッジを抑えて取引する
・あらかじめ「これ以上の損失が出たら決済する」という損切りルールを徹底する
・投資目的を明確にする(例:リスクヘッジ目的、少額で練習目的など)
デリバティブは、うまく使えば投資の世界を広げる素晴らしいツールです。しかし、その力を過信せず、常に謙虚な姿勢で学ぶことが大切です。
「仕組みを理解せずに、安易にレバレッジをかけて取引すること」が本当の危険です。デリバティブを包丁に例えるなら、その使い方を誤ると危険ですが、正しく学び、注意深く使えば、投資の選択肢を広げる素晴らしいツールとなります。
デリバティブに興味を持った方は、まずは少額から、そして何よりも「学び」から始めてみてください。デモトレードを利用して取引の感覚を掴み、損切りルールを徹底することで、リスクを管理しながら賢く投資と向き合うことができます。
WikiFXは世界中のFX業者の安全性と信頼性を評価し情報を提供する第三者機関で、FX業者の情報検索、規制機関の検索、金融ライセンスの検索、業者の安全性などを調べることができます。WikiFXを使えば、世界中の6万社以上のFX業者の安全性と信頼性を調べることができます。
→気になるFX会社を今すぐWikiFXで検索してみましょう!

【注意事項】
現在、SNSやマッチングアプリで知り合った人、SNSで誘われたLINEグループでFX投資に誘われる詐欺事件が多発しています。
もしも勧誘されたら、紹介されたFX業者をWikiFXで調べてください。
※設立1~2年のFX業者はデータやユーザーからの情報が少ないため、評価が高くても出金トラブルのリスクがありますので、投資の際はご注意ください。
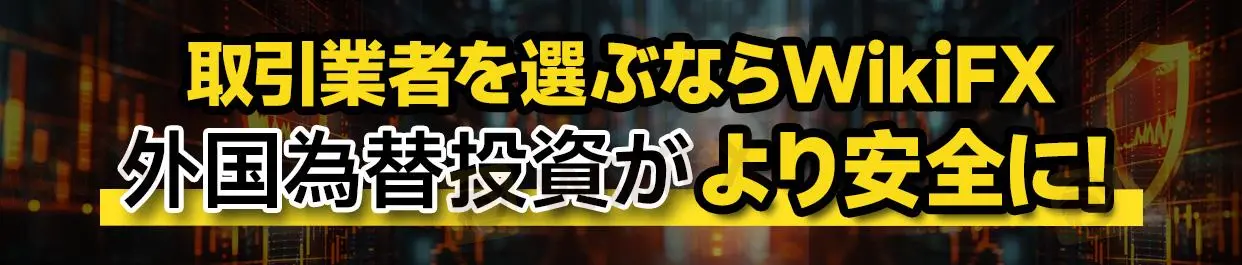
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。

今回検証するのは、近年アジア圏を中心に利用者が急増しているとされるMACRO MARKETS(マクロ・マーケッツ)です。

プロップファームは、現在、空前のマーケティング競争の渦中にあります。

長年、国外で潜伏を続けていた金融詐欺事件の重要人物が、ついにイスラエルで司法の裁きを受けることとなりました。
優良業者と悪徳業者の両方が含まれているため、選ぶ際には十分に注意してください。
